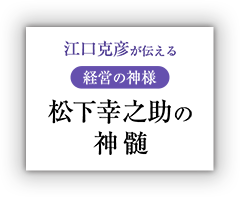
私はご承知でもございましょうが、学校へも行っておりません。いまだ手紙も自分では書かないというような状態で、あまり書いても上手ではありませんから、主旨だけ言って、みんなに書かせると。
まあ、そんなことで、才気活発(煥発?速記聞き取りマチガイ?)とか、非常にやり手であるとかというようなことは言えない状態だと自分は思うんです。世間では自分で驚くほど高く評価してくれる場合もあるんですけれど、実際はそんな偉い人間でもなんでもないんです、ほんとうはね。そういう心持ちを自分はもっているんですね。
会社へ入ってくる人はみな立派な人ですわ。体も私より丈夫やし、学問は私よりしてきているし、知恵才覚も決して私より劣っておらないと。こういう人を使っているわけですな。
私にしてみれば不足がないわけです、実際言うと。どの社員を見ても不足に感じません。みんな自分より偉いヤツやなという感じですね。
こういう気分が、どこか心の底にある。それが社員に対する態度になって現れているのではないかと思うんです。それで、比較的会社がまとまって、ぼくの言うことも、よく聞いてくれることになっているんではないかと思いますな。
(昭和38年12月5日 全国旅館経営セミナーの講演後の質疑応答)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
(江口克彦のコメント)
会社へ入ってくる人は、自分より、みな立派、体も丈夫、学問もある、知恵才覚もある。だから、どの社員を見ても不足に感じない。みんな自分より偉い人たちだと思う。
そういう自分の心持ちが社員に伝わって、社員がまとまって自分の言うことをよく聞いてくれる。そういうことで、世間は、松下は人使いがうまいと言ってくれるんじゃないだろうか。
松下幸之助さんは、このようなことを、他のところでも、しばしば、話しています。確かに、社長が、こういうような心持ちだと、社員も、なんとか社長を盛り立てようと思うものです。
勢い、社内の風通しもよくなります。お互いに言うべきことが言える。社長にも言える。となれば、社内が活気づく。明るくなります。
よく、業績が落ちてくると、大抵の場合、その原因を「社内の風通しが悪いからだ」として、「肩書呼称をやめよう。さん付け呼称にしよう」と言い出します。
5人、10人の小零細な会社は別として、業績悪化の原因が「肩書呼称」にあるということはあり得ません。いつにかかって、その原因は「社長の心持ち」にあります。
松下さんのように、社長が、社員は皆んな、自分より偉いと心底から思うだけで、人使いがうまいと評され、また、社内の風通しはよくなるということです。
要は、「社長の心持ち如何(いかん)」で、あの人は、人使いが上手いとか、そうでないとかと評され、「社長の心持ち如何」で、社内がまとまったり、まとまらなかったり、あるいは、社内の風通しがよくなったり、悪くなったりするということです。

松下幸之助は、事に当たり「深刻に考えず、真剣に考える」ことが経営では大切であると言っています。
自分でコントロールできないことを手放し、コントロールできることに集中するということではないでしょうか。
しかし、何事も一人で解決するには限界があるといわれています。一緒に解決策・打開策を考えませんか。