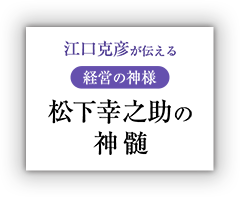
経営について学ぶいい方法?これはね、教えて悟れるものではないですよ。私は経営というものは、自得するものやと思うんです。
自得するために、あるいは人の教えを聞くとか、自分で体験してみるということは、それは必要でしょう。しかし、これは教えられるものではないです。これはもうみずから会得せねば仕方ないですな。
なにか自分でいろいろ考えてみて、そしてみずからそこに悟るものを持たなかったら、いかんですな。経営というようなものは、教えられるものではない。
経営学は教えられますよ。経営学というものは、経営学者に教えてもらったら、ある程度、分かります。
しかし、経営というものは、生きた経営というものは、教えられないです。これは、もうその人が、自分で体得するものですわ。
経営は、教えられるものではなく、習うべきものではなく、みずから体得するものだと思いますな。それが一番の近道ではないかと思います。
(昭和42年12月7日 経済同友会東西会での講演)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
(江口克彦のコメント)
簡単に言えば、経営とは、社員の心を一つにまとめ、一つの目標に向かって進み、その目標を達成することと言えるでしょう。しかし、その社員の心をまとめることが難しい。
社員の心が、全員同じということはあり得ません。加えて、その一人ひとりの心も、常に一定ということもあり得ません。千変万化します。
心は、コロコロと変わるから、心だというのも、あながち否定できないと言います。まさに、コロコロと心の変わる社員をまとめる。加えて、経営者自身の心も変わる。
変わる心と変わる心を一つにまとめるのに、一定の方法はありますまい。教科書をいくら読んでも、教科書でいくら教えられても、教科書外のことが起こる。起こるのが当たり前の経営を、学ぶいい方法などあるはずがありません。
経営をうまく身につけようと思うなら、また、いい方法を学ぼうと思うなら、「経営の海」に飛び込んで、なんとか浮こう、なんとか泳ごうと、みずからもがく以外に方法はないでしょう。
その、もがいているうちに、浮くコツ、泳ぐコツを覚える。自得する。経営のコツ、いい方法も、もがいて、もがいて、体得、自得する以外にないのではないか、と松下幸之助さんは言っています。
経営書を読むのもいい、セミナーを受けるのもいい。しかし、それをそのまま、鵜呑みにして実行するのではなく、さらに自分なりの経営のコツ、いい方法を自得し悟り、生きた経営を、お互い心掛けたいものです。
「百聞は一見にしかず、一見は経験にしかず、経験は自得にしかず」ということでしょうか。
(※しかず〈如かず〉=及ばない)

松下幸之助は、事に当たり「深刻に考えず、真剣に考える」ことが経営では大切であると言っています。
自分でコントロールできないことを手放し、コントロールできることに集中するということではないでしょうか。
しかし、何事も一人で解決するには限界があるといわれています。一緒に解決策・打開策を考えませんか。