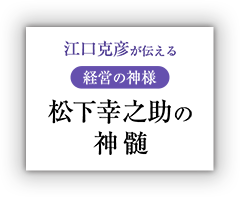
今度の戦争(大東亜戦争)で、若き青年、あるいは学徒動員された人たちは、一路殉国の精神に燃えて、あるいは特攻隊員になって戦死された。そういう殉国の青年をして犬死というような人があるとするならば、これは私は許せないことだと思います。
その若き青年たちの死は決して犬死ではなかった。そういう青年たちの尊い血が流されたということが、アジアなりアフリカの幾多の植民地の国々が独立した一つの基礎になったということを考えますと、その独立は、一面において、日本の若き学徒たちなり青年たちなりによってもたらされたということが言えると思うのです。
しかし、そのことが、われわれ国民の間で叫ばれておりますかどうか。おおかたは叫ばれておりません。のみならず、独立をかちとった国の人びとも、はっきりとそういうことを言っておられません。
これは私は、日本が四年間戦い抜いたことによって、そういう機会が生まれたということを、はっきり知ってもらうべきではないかと思います。
もし日本に実力がなくして、戦争が一夜にして敗北する、あるいは短期間にして敗戦の憂き目をみるというようなことがあったならば、植民地は解放されなかっただろうと思うのです。
そのようなことを考えてみるとき、われわれは、犠牲になった若き学徒たちなり青年たちに、“諸君は、まことに気の毒であったけれども、しかし、冥(めい)していただきたい。諸君の犠牲によって、多数の国の虐(しいた)げられた人びとがみずから独立し、やがて立派な国に成長しようとしている。決して諸君は犬死ではなかった”という言葉をはなむけにすべきだと思うんです。
※冥する=安心して、往生すること。
(松下幸之助著『一日本人としての私のねがい』昭和43年刊)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
(江口克彦のコメント)
最初から、日本がアジア諸国を完全独立させるために軍を動かしたとは、必ずしも言えないかもしれません。
しかし、日本が侵攻したことによって、白人による支配が終わり、アジア諸国が独立したことは、結果としては事実でしょう。大東亜戦争は侵略戦争だ、無意味だったと言い募ることは、殉国の精神に燃えて、あるいは特攻隊員になって戦死した、そのときの若き青年、学徒の御霊(みたま)を足蹴(あしげ)にするのと同じこと。
大東亜戦争期を、実際に共に生き、戦死した若者たちへの、松下幸之助さんの悲痛な鎮魂の話に、私たちも理屈、偏見を超えて、素直に耳を傾けてもいいのではないでしょうか。

松下幸之助は、事に当たり「深刻に考えず、真剣に考える」ことが経営では大切であると言っています。
自分でコントロールできないことを手放し、コントロールできることに集中するということではないでしょうか。
しかし、何事も一人で解決するには限界があるといわれています。一緒に解決策・打開策を考えませんか。