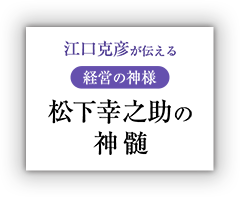
昨年は、まことに経営全般にわたり多事多端、非常に困難な年でしたが、皆さんは終始一貫ご奮闘下され、感謝にたえません。
しかし、それにもかかわらず、わが社の経営の上に、その効果が著しく現れるということに至らなかったのは、非常に残念なことであって、従業員の皆さんの努力に対して、酬いることもまことに薄く、かつてそのようなことのなかった賞与の支給もできないという状態に陥りました。
また、定期昇給も、しばらく保留しておかなければならないという窮状に推移したことは、まことに面目ないことであって、皆さんにお詫びせねばならないと思います。
われわれは長き一生に、ときに日陰のうちに日を送ることもあり、あるいはまた得意絶頂に立って欣喜雀躍するというようなこともあろうと思います。
そういうところに、いわゆる人生の味わいというか、深みというものがあるのであって、私は、そういう両面を味わい得た人においてのみ、人生を語る資格があるといってもよいと思います。
そういう体験を、わが社としては今度初めて得たのであって、今後、松下電器は、社会を語り、人生を語り、事業を語る資格が、初めてできたものであると考えてもよいと思うのです。
そう考えてくると、昨年の最悪の年は、必ずしも最悪の年にあらず、まことに有意義な年であったと言わねばなりません。われわれは常に、いかなる場合、いかなる時にあっても、光明を見出していき、よくないことがあっても、それを福に転じて進んでいくということに、事業遂行の心構えを樹立しなければならないと思うのです。
(昭和24年1月10日 経営方針発表会 話の冒頭)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
(江口克彦のコメント)
前年の松下電器は、資本金4,630万円にもかかわらず、その9倍近くの4億円の借入れ金、3億円の支払い手形、未払金の重荷に苦しみ、給与も10月から分割払いを余儀なくされています。
松下幸之助さんの経営は、常に順風満帆のように思う人がいるかもしれませんが、このような塗炭の苦しみのときが数回あります。しかし、それらを都度、乗り切ってきたからこそ、「経営の神様」となったのだと思います。
ここで、思うのは、こうした状況になっても、なお、経営を投げ出さず、かつ、社員に窮状を招いたことを率直に詫びていることです。
時代が悪いから、ましてや、お前たち社員の働きに欠けるものがあったからなどとは、ひと言も言っていません。まさに、「責任は私一人(いちにん)にあり」と語っている。
さらには、失意のときも得意のときも経験してこそ、人生においても、経営においても、深みが出てくる。と同時に、「よくないことがあっても、転じて福にすれば、そのよくないことは、よくないことではなくなる」という松下幸之助さんの言葉は、トーマス・カーライルの「永遠の肯定」に類似しているようにも思います。
いかなる不況も、いつか、終わります。そのとき、経営者であるあなたは、社員にどのような話をしようと考えているのでしょうか。

松下幸之助は、事に当たり「深刻に考えず、真剣に考える」ことが経営では大切であると言っています。
自分でコントロールできないことを手放し、コントロールできることに集中するということではないでしょうか。
しかし、何事も一人で解決するには限界があるといわれています。一緒に解決策・打開策を考えませんか。